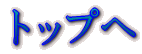「華代ちゃんシリーズ・番外編」 「ハンターシリーズ」 「いちごちゃんシリーズ」  作・真城 悠 |
ハンター・シリーズ31 『今宵、貴方に人形を』 作・てぃーえむ |
「ほわわゎゎ」 ハンター組織本部。その食堂の一席で、いちごはあくびを漏らした。それから目をこすって、頭を振るったが、まぶたは半分閉じている。普段は輝きを放つポニーテールも、今はしおれ気味だ。よく見れば少しお肌が荒れていた。 「もぐもぐ・・・いちご、夜更かしは美容の大敵だぞ・・・むきゅむきゅ、ずるる」 隣の席に座る五号が、ミートスパゲッティを頬張りながら言う。 「しゃあないだろ・・・・・・、仕事なんだから」 「だからって徹夜すること無いだろ」 いちごの仕事熱心さに、五号は少々あきれ気味のようだった。 「そうだな。人には安息が必要だ。それは戦士であろうと変わりはない」 「ふわあ・・・それもそうだが・・・ってあれ?」 突然割り込んできた声に、いちごは首をかしげた。涼やかで耳に心地よい声色と、それに似つかわしくない男っぽい口調。それに関しては何も言えないいちごだが、聞き覚えのない声ではあった。 「君は・・・」 いちごは初めて、向かいの席に座っている少女に気が付いた。十四、五歳ほどの、ショートカットの美少女。室内なのに、なぜかコートを羽織っている。青みかかった緑の瞳が印象的で、それで彼女が誰か思い出した。ボスが連れてきた幼い名探偵。いつか新聞の写真で見たときは長髪で、深窓の令嬢然としたやわらかな雰囲気だったが、目の前の少女は真逆の気配をまとっていた。 「ええと、浅葱ちゃんだったっけ? いつの間に?」 「あなた達が来る前からいたぞ。ところで私は千景でいい。ちゃんは入らない。断じて入らない」 その少女、浅葱千景は頷いて、天ぷらそばをすすった。 「わ、わかった。俺はいちごと呼んでくれ。こっちは五号」 「あいわかった」 自己紹介を終えたところで、五号がいちごの腕を突っついた。 「知り合いか? こんな子うちにいたっけ?」 「なんだ、お前知らないのか。ほれ、最近まで紙面を騒がしてた探偵だよ」 その言葉で、五号は手をぽんと鳴らした。 「探偵。知ってるぞ。捜し物したり、浮気調査したり、謎の美女の依頼を受けて大事件に巻き込まれる職業だ。それがなんでうちにいるんだ?」 「ボスが連れてきたんだよ・・・ふわああ」 いちごは見るまでもなく眠そうだ。 「私のことなどどうでも良い。今の君に必要なのは睡眠だ。眠ることを勧める」 「ああ、そうだな・・・。それじゃあ俺は失礼するよ・・・じゃあな五号。それと千景」 千景に促されたいちごは、今までで一番大きなあくびをすると、食器を持って立ち上がった。そして、危ない足取りで去っていった。 「おっ! おおおおっ! おおおおおおお!!」 夕食を終え、本部内をぶらついていた千景は、突然その咆哮を耳にした。 取り敢えず振り返ってみる。するとつっこんでくる五号の姿が。目が血走っている。 「どええ!?」 そのすさまじい形相に、たまたま近くにいたハンター二十三号がびっくり声をあげた。 千景はぶつかる直前、後ろに倒れつつ五号の懐をつかむと、巴投げの要領で投げ飛ば・・・・・・さずに、ころりと回転。一瞬後、千景は五号を片足で踏みしめて立っていた。 「おおっ」 鮮やかな手並みに二十三号は感動した。 五号は抑えられたタコみたくじたばたしている。 「のおおおおおおう!!」 「落ち着け」 千景は懐から青柳の『一口ういろう』(さくら)を一個取り出して、五号の口につっこんだ。千景は和菓子を常に携帯しているのだ。もちろん運動時のエネルギー補給のためである。 「ぐにゅぐにゅ・・・ごくん。あ、あんたはさっきの探偵!? たいへんなんだ!」 「なにが」 「盗まれたんだよ、宝物が!! ちょっと飯喰ってた隙に!!」 「そうか。災難だったな」 明瞭を得た千景は、五号から足をどけるとその場を去ろうとした。が、足を捕まれた。 「見つけ出してよ探偵さん」 「いやだ」 「中松屋の『水まんじゅう』(栗餡)あげるから」 「話を聞こう」 千景は未だ寝ころんでいる五号の手を取った。 「な、なんて現金なんだ・・・!!」 千景の変わり身の早さに、二十三号は人知れず戦慄していた。 「随分と荒らされているな」 それが、五号の部屋を見た千景の第一声だった。 「いや、これで普通だけど」 「・・・・・・。で?」 「これを見てくれ」 五号は部屋の隅にある開かれたままの金庫を示した。 早速、千景は金庫を調べる。 とてつもなく強固である事は見れば分かった。アルファベットのボタンが付いているが、デジタル方式ではなく、カラクリによる鍵になっているようだ。よくよく調べると、複雑な機構になっていて、短期間で無力化するのはまず不可能だろう。 次に、その周辺。証拠探しより、部屋の真ん中に立つ『もったいないお化けトーテムポール』や寝ころんでいる『腰蓑付きモアイ像』が気になったが、なんとか自制する。 証拠探しは後回しにして、千景は感覚を広げた。こうすることで千景は、最大半径二十五メートル内の気配を読むことが出来るのだ。探偵と呼ばれる前、暗殺者時代のさらに以前、傭兵時代に身につけた技術だった。 「ほう・・・」 室内に異質な気配が残っていることに気が付く。それだけで十分な収穫だ。 「ちなみに、何が入っていた?」 すぐに探知を終えて、千景は尋ねた。 「いちごの・・・人形だ!」 五号は声を絞り出すかのように答えた。 「・・・・・・。いちごとは・・・あの少女の名だったな」 「ああ。あれは手作りなんだ。布地はいちごのシャツを使ったし、綿は、いちごの下着をほぐして作ったし。目の部分なんて、いちごのメイド服のカフスボタンを使ったんだ・・・・・・!」 五号は涙を流してそう宣った。 こいつ、そのうちいちごに殺されるぞ。そう千景は思ったが、口には出さない。 「今日の夕方、やっと完成して・・・。ちゃんと金庫にしまったのに・・・。あの金庫が破られるなんて!」 「随分信頼してたんだな」 「だって、開発部の奴らが保証したし」 「ふむ」 千景も、ここの開発部の優秀さは聞かされている。彼らが保証するほどの金庫。鍵穴もなく、通常のツールでは対応出来まい。まず開けられないだろう金庫をたやすく開いたのなら、方法はただ一つだ。 「この金庫のパスワードだが。何桁だ?」 「え。ええと・・・11桁」 「いちごのフルネームは?」 「半田いちご」 「・・・・・・」 ものすごくわかりやすかった。 千景はしゃがみ、一度金庫を閉めると、ボタンを操作した。ちーんと音が鳴って、金庫が開く。 「な、なんで開けられるんだ!?」 驚愕する五号を尻目に、千景は次の質問をした。 「人形と、金庫についてどれだけの人が知っている?」 「え? あー、うーん・・・。ひとりだけ、かなあ。じつは飯前に自慢したんだ」 「誰だ」 「七号だけど」 聞き覚えがあった。 「確認するが、夕食前には、人形はあったのだな?」 「うん、てか、仕舞ったのは食堂に出かける前だし」 「ふむ。いちごの人形・・・か。同僚ならいちごが徹夜していたことは知っている筈だな。・・・なるほど、そういうことか」 「どういう事だ?」 「つまり、七号が犯人だ」 千景は、なんの物的証拠も見つけないまま断言した。 「うおおおおおおおっ!!」 雄叫びをあげて突っ走る五号の後を追いかけていくと、本部内にいくつかある広間の一つにたどり着いた。 そこに置かれたテレビの前で、男性一人と女性二人が談笑しているのが見える。 「なあああなああああごおぅおおおお!!!!」 五号は男性の胸ぐらをつかむと、激しくシェイクした。 「落ち着け五号」 千景は五号の首をつかむと、足払いした。 「ぐほう!!?」 背中からたたき付けられた五号に、千景はすかさず懐から大須の『ないろっ子』(白)を十コ取り出して、口につっこむ。 五号は沈黙した。 「失礼。貴方が七号?」 「うん、そうだよお嬢さん。ところで君、見かけない顔だけど・・・?」 七号は、おっかなびっくりな表情で訊ねてきた。それでも笑顔なのは、千景がかわいらしい少女だからだろう。 「ふむ・・・。私は・・・」 千景はじっと七号を見つめて、彼の気配が部屋に残っていた気配と同じであることを確認する。 「私は浅葱千景という。以後お見知りおきを。後、これを」 「はあ」 千景は、懐から川上屋の『膝栗毛』を取り出すと、七号に手渡した。 「・・・・僕、甘い物はあんまり」 七号は申し訳なさそうにつぶやいた。 「何だと!?」 甘い物好きの千景は衝撃を受けた。 「甘い物が嫌いとは・・・・・・信じられん。ま、まさか貴方は無糖派か? まずいコーヒーにも砂糖を入れず『やっぱコーヒーはブラックだよね』などと抜かすのか! この愚か者め!?」 千景の激しい物言いに、七号は取り敢えず頭を下げた。 「あーいやその。ごめん。僕が悪かった。ゆるして」 「・・・・・・。すまない、私としたことが年甲斐もなく取り乱してしまったようだ」 千景は少々乱れた息を整えると、七号から『膝栗毛』を取り返し、一口で食べた。 「もぐもぐ。さて、慣用句に満ちた挨拶はこれまでにして、次に進もうか」 「もはやどこからどうつっこめば良いんだか分からないから、先に進むのは賛成するけど」 「うむ。では質問の時間だ。私は間怠っこしいのが嫌いだから単刀直入に言う。五号が所有していた人形が奪われた」 「ぎくり」 途端、七号が言葉を漏らした。 「君だろう」 「な、何のことかな。全く分からないなあ。ねえ? 水野さん、沢田さん」 「そうかな」 「さあ?」 「ほほら見ろ。そそそそれに、証拠はあるのかい?」 七号は露骨に怪しかった。 「物的証拠は探していないが・・・」 千景はため息を吐き、答えた。 「私の直感がそう言っている」 「それだけー!?」 「いや、君の気配がはっきり残っていたし。さて、これが何か分かるな?」 懐から銃を取り出した。そして、七号の額に照準する。 「モデルガンだろ? BB弾が飛び出るヤツ」 「違う。これはザウエルP230カスタムのエルたんだ。チタン製でな、渋い色合いだろう。それにおしゃまなフォルムが愛らしい」 「そ、そうなのかな」 「それと、このエルたんに詰まっているのはゴム弾だ。私は人殺しは卒業したからな」 「なんだか恐ろしいことを言ってる気がするけど・・・・・・」 「雰囲気の問題だ。まあ、喰らっても死にはしないが、痛いぞ。なにせ暴徒を無力化するための物だからな」 「うう、やだな・・・」 そんな二人のやりとりの合間、女性二人はこそこそ話し合っていた。 「そう言えばあの女の子・・・見たことあるわ」 「ボスが連れてきた子でしょ。確か、有名な探偵さんだったと思うけど」 「うん。そうね。でもなんだか評判と違うわねえ・・・」 「それ以前に、やり方が根本的に探偵じゃないような」 水野さんと沢田さんは、いつの間にやら手を挙げて跪いている大人な七号と、彼の頭に銃口を押しつけている子供な千景をまじまじと見た。 「そもそも君、何でそんなの持っているんだ?」 「武器倉庫の主にもらったのだ。武器を持つのは乙女のたしなみ、そう諭されてな。なるほどなと思った」 「思うなよ!」 「まあ良いじゃないか。たかがゴム弾だ。見ろ」 千景は証拠と言わんばかりに、テレビのそばに置いてあった鉢植えを撃った。 ばん! ぼかん!! 鉢植えは、派手な音を立てて砕け散った。 「あれ?」 千景は、小首をかしげた。 「あれじゃねえー!?」 七号は絶叫した。 「どうやら弾を間違えたらしい。まあ気にするな」 「気にするわ! てか、その物騒な物を向けるな!」 七号は硝煙を放つエルたんを払おうとしたが、その前に千景は一歩下がった。もちろん銃口は七号を向いている。 「撃たれたくないなら、人形の在処を吐くことだ」 「ああ、もう! 君は探偵だろう!? 気配だなんて不確かなこと言わないで、探偵らしく推理してみせろよ!」 もはや彼は逆ギレ気味だ。しかし千景は至って冷静だ。 「なぜ私が探偵をしていたと知っている」 「新聞で読んだ!」 「ふむ。だが今はどうでもいいことだ。この事件に推理など必要ないからな。君が犯人なのは事実だろう?」 「そりゃそうだけど・・・なんだかなあ・・・」 とうとう七号は、肩を落として自白した。あらゆる期待を外された、そんな感じだ。だが千景は気にしない。 「そらみたか。さあ、人形はどこだ」 「いちご先輩に渡しましたよ・・・。いや実は人形を手にいれてすぐ、いちご先輩が現れて。いろいろ言い訳したその結果・・・」 「なるほど」 千景は七号のやる気のない説明を一言で断つと、倒れてる五号を見下ろした。 「だそうだ、五号」 「ひぃいいいやっほうううううぅ!!」 途端、五号は『ないろっ子』(白)をすべて飲み干して、けったいな歓声を上げて走り去った。 「あ、ちょっと!? いちご先輩今きっと寝てますって、ねえ!?」 そんなことを言いながら七号は立ち上がり、五号の後を追いかける。 刹那、彼の唇は笑みの形を取っていた。にやり。 「・・・・・・。まあ、事件のことは水に流そう。お二方、これはお近づきの印に受け取ってくれ」 千景は、沢田さんと水野さんに両口屋の『荒磯』を三個ずつ手渡すと、七号の後を追ってかけだした。 後は、和菓子を手にした事務員が二人。 「一体なんだったんだか。それにしてもこれ、しらないお菓子だけど・・・あ、おいし」 「どれ・・・ほんとだ。これって黒砂糖?」 それから三十秒後。 「っ! きゃあああああああ!」 「ぐごはあああああああああああ!?」 という二つの悲鳴が寮内にこだました。 「話はわかったが。それといちごの引きこもりはどうつながる?」 『水まんじゅう』(栗餡)を食べながら、ボスは予想はしつつも、千景に疑問を投げかけた。テーブルの箸に、さりげなく鉢植えの請求書が置いてある。 「はい。五号がいちごの部屋へ進入した時、彼女は睡眠中でした」 請求書を無視しつつ、やはり『水まんじゅう』(栗餡)を食べている千景は、ほうじ茶をすすりつつ説明を始めた。普段とは違い、表情が年相応なのはボスの前からだ。 「これがその時の写真です」 取りだした写真には、Tシャツとトランクス一枚で眠る十七、八の美少女が写っていた。しかもかわいらしい人形を抱き抱えている。布団に広がる長髪がまた、良い雰囲気を演出していた。 まさにベストショット。 「これは誰が撮った」 「七号です。初めからこれが目的だったようですね」 「・・・・・・。ななちゃんめ」 「直後、五号はいちごに抱きつきました。その結果・・・・・・五号は目を覚ました彼女の攻撃を受けて沈みました。全治三週間だそうですが、すでに動けるようです。ちなみに七号はすぐに部屋を出たので助かったのですが。しかる後に、私が人形について説明したところ・・・・・・」 「引きこもった訳か。それにしても、迷わずに七号が犯人だと即断したのは?」 「単に、状況からして彼しかあり得なかった、と言うことです。それに彼はわざと、分かるよう仕組んでいたようです。後で調べなおしたら、証拠がいくつか出てきましたし」 つまり七号は、茶番劇を仕組んでいた、ということだ。本当の目的を達成するために。その成果が、この写真なわけだ。 「そうそう、実は先日、何者かから逃亡しているうさぎ耳少女をかくまいまして。その時に七号について聞きました。そうでなければ、さすがに写真のことまでは分からなかったでしょうね」 千景は写真を懐に戻した。ボスは密かに残念がった。 「まあ、君が部下達と親睦を深めるのはうれしいことだが・・・」 ボスはほうじ茶をすすり、 「取り敢えずいちごを引っ張り出してくれないか。今日は体力測定なんだ」 「・・・はい」 ちなみに。 いちご人形は無事、五号の元へ返された。 「ここが何もない心の中として。耳を澄ませたら、何が聞こえると思う?」 小さなバーの片隅で、翠碧の瞳の少女へ投げかける、意味のない質問。 聞くまでもなく、答えなど分かっていた。 何も、聞こえはしないだろう。 それでも。 そこには響いている声がある。 声があるのだと。藤美珊瑚は信じていた。 次回 『誰にも届かない、その歌を』 おたのしみに。 |