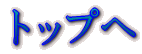「華代ちゃんシリーズ・番外編」 「ハンターシリーズ」 「いちごちゃんシリーズ」  作・真城 悠 |
ハンター・シリーズ69 『公園にて』 作・てぃーえむ |
| > |
|
真夏の太陽がぎんぎらぎんに輝く中、洋風の少女と和風の少女が並んで道を歩いていた。 洋風の少女は、ゴスロリチックなワンピースを着て、手にはフリルで飾られた黒い日傘。でもなぜか男物のコートを羽織っていて全然似合っていない。しかも暑そうだが、当人は涼しい顔で、足音も軽やかというかむしろ音も立てずに歩いている。 和風の少女は、長い銀髪を紐で結び、浴衣姿が涼やかだ。右手に和傘、左手に刀袋を持って、やたらとなじんで見えた。歩き方からしてみても、使い手であることは明白だった。 千景と疾風である。 疾風は、こんな日なのにコートを羽織っている千景を見ていたが、やがて声をかけた。 「浅葱千景」 「?」 「なぜコートを羽織っている」 「うん?」 至極まっとうな質問に、千景は始めきょとんとして、それからやれやれと言わんばかりに首を振った。 「疾風。君は剣士としては一流だが、探偵についての知識は小学生並みと言わざるを得ないな」 「な、なんだと?」 「探偵とは、コートを羽織るものだ。どの本にもそう書いてある。それはみんな知っていることなんだ。だから私も羽織らねばならない」 「なんなんだその理屈は!」 疾風は怒鳴った。琥珀色の瞳が燃えている。そんな彼女に千景はまたも首を振った。 「君は、道理というものを知らないのか」 「そんな道理を知っている奴は貴様だけだ!」 「そうか……? む、見えたぞ」 千景の目線の先には、クレープ屋があった。風に乗って甘い香りが漂ってくる。とてもおいしいと近所でも評判であり、今もこの暑い中ちょっとした行列が出来ている。 「よし疾風、並んでこい。私は木陰で休んでいるから」 「貴様も来い!」 疾風は、逃げようとする千景の腕を掴んで列に並んだ。 五分ほどして、二人はようやく売り子さんの前までたどり着くことが出来た。 店員さんは、そこかしこ控えめにフリルで飾られた可愛らしい制服を着ていて、制服マニアにも好評だ。 千景と疾風はメニューを三秒間見つめると、 「宇治金時を」 「カスタードホイップを」 同時に言った。 程なく届いた目的の品を受け取ると、二人は財布を取り出してお金を払い、近所にある公園へと足を向けた。時々、謎の少女が姿を見せると一部で評判の公園である。 日傘を閉じて、木陰のベンチに二人並んで座り、クレープを食べる。 「むぐ。おいしいな」 「行列が出来るだけのことはある」 「むっ、なんだあれは?」 不意に千景が遠くを指さした。つられて疾風がその方を向くが、木々の向こうで行き交う車が見えるだけだった。 「? なんだ、なにもな……」 「ぱくっ」 「うわああああああ!?」 「そちらもおいしいな」 「貴様ああ!! よくも俺のクレープをぉ!!」 「そう怒るな。剣士がこの程度で怒ってどうする」 「そういう問題じゃないだろう!」 疾風はちょっと涙目だった。 「やれやれしかたない。ほら、私のを食べて良いぞ」 「ぱくぱくぱくっ」 「さ、3口も」 「はっはっは! 天罰だ」 そんなやりとりをしつつ、やがて二人はクレープを食べ終わる。 一息ついたところで、千景は言った。 「まさか君と並んでクレープを食べる事になるとは、世の中解らないものだな……。しかもあれほど尖っていた君が、今では可愛らしいことになってしまった」 「尖っていたとはなんだ。貴様も人のことが言えた義理か!」 客観的に見て、二人の可愛らしさはどっこいどっこいだった。 「そう怒るな。しわが増えるぞ」 「増えるか! だいたい前から思っていたが、なんなのだその格好は! ま、まさか貴様にそんな趣味があったのか?」 疾風は、千景のゴスロリ風なファッションを指さした。確かに、普通はあんまり見かけない格好ではある。 「ああ、実はそうなんだ」 「肯定するのか!?」 「さあて」 ほーっほっほっと、千景は表情を変えぬまま某海苔のCMのおじいさんみたいに笑った。 話にならない。 疾風は、怒気をため息にしてはき出すと、表情を改めた。 「……それで、用件はなんなのだ。まさかクレープを食べに来た訳じゃあるまい」 話があるからちょっと付き合えと誘ったのは千景だった。御菓子を買いに出かける以外ではほとんど外に出ない千景がわざわざ外へと誘うのだから、よほどの話に違いなかった。 「うん? クレープを食べに来たのだが」 「……」 疾風は三白眼になった。 「いや冗談だ」 このままでは斬殺されそうだと思ったのか、千景は本題に乗り出した。 「用件というのはこの世界と私のことだよ。君はここをどう思う?」 疾風は一瞬だけ考えて、言った。 「……俺の知っている世界じゃないな。貴様がそんな形になっているだけじゃない。この世界には……浅葱千景がいないのだ」 暗殺者の浅葱千景が存在しない。だから、彼に殺されたはずの人びとも生きているし、彼が関わったとされる事件も疾風の知るものとは違う結末を迎えていた。 「その通り。ここには君の知っている浅葱千景は存在しない。代わりに私がいる、そういう世界なのだよ」 「ここはパラレルワールドとでも言うつもりか」 「そうとも言えるし、違うとも言える。主観で変わるな。どちらにせよ、ここをそのようにした者が存在する」 そんなことが出来そうな存在を、疾風は一人だけ知っていた。 「真城華代か……。では彼女に依頼をした者がいると言うことか」 強大な力を誇る真城華代。彼女は基本的に、依頼でのみその力を発揮する。 「そうだ。かつて紙面をにぎわす名探偵が存在する世界を望み、それを華代に依頼した者がいた。そして華代がその望みを叶えようとしていた際、私はたまたま依頼で彼女の殺害を謀っていた。そのことを察知した華代は依頼をかなえるついでに私を……懲らしめる心つもりでもあったのかもしれないな……、ともかく探偵役を私に選んだということだ」 そう言う千景の顔は普段通りだった。ただ事実を述べているだけで、このことについてはこれといって思うことはないようだった。 「思うにこの世界は上書きされたのだろう。彼女は、浅葱千景が探偵として存在している世界を適当に検索し、目についたものをコピーした。そして我々がいた世界にペーストしたのだろう。あるいは世界のデータを、我々の世界に移したか。君と私に上書き前の記憶が残っているのは、ちょっとしたエラーを起こしたようなものか」 上書き。なんだそれは。 言っている意味が分からず、疾風は首を振って見せた。 「まったく訳がわからんぞ。だいたい一体どんな力があればそんな事が出来るのだ?」 「彼女の力については確かなことは言えない。だが推測することは出来る。君はパソコンを扱えるな?」 「? ああ……使えるが」 「世界はパソコンにたとえられる。OSは世界法則であり、一つのフォルダは一つの世界であり、その中のファイル群が人であり物であったりする」 「まあ、解らなくはないが……」 「華代自体もファイルの一つだ。ソフトと言うべきか……もしかしたらウイルスかもしれないな。どれにしろ、そいつはひょこひょことフォルダの海を気ままに移動するプログラムだ。そして、あるアプリケーションソフトを呼び出すことが出来る」 「……。アプリ?」 「そうだ。そのアプリの力は大きく分けて二つ。一つはフォルダつまり世界の検索とコピーペーストだ。そしてもう一つは、プログラムの改ざんだ。OSの重要な設定も変更できるだろう。まあ強力なユーザー支援ソフトみたいなものがあって、そいつを利用しているのだろう」 疾風は腕を組みつつ考えた。要するに、ソフトの機能がそのまま華代の持つ超能力にたとえられているのだろう。 問題となるのはアプリの機能だ。千景はプログラムを編集できると言った。これは人を性転換したりする力のたとえだろう。コピーペーストというのは、この世界にたいして行ったことなのだろう。 「ん?」 ここで、1つ引っかかった。 「呼び出す?」 「ああ」 「まさか、華代の力は自身の物では無いと?」 「性転換をはじめとする世界に干渉する力は、借り物の力だという可能性がある」 「根拠はなんだ」 「華代は複数存在するが、使用している力自体はまったく同質のものだ。だがこれまでの被害報告書を見る限り、練度はまちまちで、変なところで細かいくせに、融通か効きそうで効かない。だがシステムが別に存在していて、そのシステムを利用していると考えれば納得がいく?」 「なぜ疑問系なのだ」 「確証がないからだが。さらに言うならば、ハンター能力。これもアプリを利用する能力ではないだろうか。まあ限定された機能しか使えないようだが。それとハンターの能力は華代被害者にしか効かないが、これはあらゆる存在にはプロテクトがかけられているからではないだろうか。外からそう簡単にプログラムを弄られては適わないからな」 「まあ、それはそうだな」 「華代とハンターとの違いはそこだろう。華代はそのプロテクトを解除することが出来る。自身の能力なのか、アプリの機能を使っているのかは解らないがね。だが、ハンターには出来ない。華代被害者にのみ力を発揮できるのは、華代がプロテクトを解除した後だからだろう」 「だが被害者の中には、ハンターの力が通じない者がいるじゃないか」 実際、ハンター組織内には被害を受けて戻れないハンターが数多く存在していた。 「ふむ、そうだな。華代被害には2パターンに分けることが出来る。まず、華代と接触し、依頼をした結果、自身、あるいは自身を含めた周りの人びとが変身させられた場合だ。この場合は、ハンター能力で戻すことが出来る。次に、誰かが華代と接触し、依頼をした結果、他人が変身させられた場合。この場合は、ハンター能力で元に戻すことは出来ない」 千景は人差し指を立ててくるくる回しつつ、説明を続ける。 「華代は力を行使するとき、依頼主に依頼を聞き、それを……おのれの解釈の元でだが……果たす。この依頼を聞くという行為が、存在にかけられたプロテクトを解除する為の契約になっているのだろう」 「け、契約か」 パソコンはどこへ行ったんだと思ったが、空気を呼んでそれは言わないでおく。 そんな疾風の思いを知ってか知らずか、千景は大きく息を吸うと、 「いわゆる巻き込まれ型の場合にハンター能力が通用しないのは、プロテクトがかかってしまっているせいなのだろう。何故そうなるのかは……これはどうにも解らないな。プロテクト解除というシステムにバグがあるのかもしれない。依頼主を含めずに別の存在のプロテクトを解除した場合、すぐにプロテクトが即座に復活してしまうというバグが。……いや、あるいは逆かもしれないな。依頼主または依頼主を含む存在のプロテクトを解除した場合、プロテクトはすぐには復活せず長時間をおく必要が出てくるというバグかもしれない。ああそうそう、解除されるのは、基本は華代が指定した存在のみだろう。もっとも彼女はアバウトな性格なので、適当に範囲を決めてその内に存在する者に対してプロテクト解除を行っているようだが。つまり、華代の力は以下の通りだ。空間を移動する力。契約により存在のプロテクトを解除する力。そして強力な機能を持ったアプリを呼び出し利用する力……あるいはそれも華代自身の力かもしれないがね。ああ、不老不死もあるか。あとは、運命に守られている気もするが……それはよく分からない。重ねて言うがこれは推測だ。詳細な実験の結果というわけではないし、華代自身に関する情報もあまりにも不足している」 早口で一気にしゃべりきった。あー疲れたと言わんばかりに息をつく。そしてふにゃりとだらけた。 そんな姿を見て疾風はふと思った。まさかこいつ、自分で言い出しておきながら、話してる途中で面倒になってきたんじゃないだろうな。だとしたらなんて気まぐれな奴なんだ探偵のくせに。 疾風は千景を軽くにらんだ。 すると千景はその視線の意味に気がついたらしい、わざとらしくこほんと咳をしてたたずまいを直した。図星だったのだろうか。 「まあ華代の力はともかく……。この世界も私も、世界と私を弄って作ったものではないと言うことだ。この世界は元々あったもので、私もこの世界で14年を生きてきた。これは確かなことだ。その記憶は……まあ『前世』の記憶の弊害か喪失してしまっているが、おぼろげに覚えていることもある。いずれすべて思い出すだろうし、その時、もしかしたら『前世』の記憶はなくしてしまうのかもしれない。私は、精神的には君の知る浅葱千景に極めて近い存在であるが、物理的には全くの別人で、真の意味で君の知る浅葱千景はもういない。この世界の視点から見るならば、もとより存在しないと言うべきか」 それで悟った。目の前にいる浅葱千景は似て非なる物だと、もう復讐をする必要はないのだと、この少女は言っているのだ。疾風は首を振った。 「……それでも俺は覚えているのだ。消えてしまった世界のことも、その世界でされたことも、誓ったことも。貴様は別人になったのかもしれないが、俺を覚えている。ならば俺は貴様を倒さねばならない。決着をつけねばならない。世界がどう変わってようと、知ったことか」 そう断言してみせると、千景はあきれた顔をして見せた。しかし同時に、その回答をあらかじめ予想していたようでもあった。 「やれやれ。私も随分憎まれたものだな。しかしこの前やり合って確信したが、私は『前世』の記憶のおかげでそれなりに戦えるが、戦闘力では君には遠く及ばないぞ? 全力で斬りかかられたら、その速さに反応は出来ても、私の体が追いつかないからな。確実にやられる」 「むっ……」 などと言われて、疾風は言葉に詰まった。そんな彼女の顔が面白かったのか、千景は楽しそうに目を細めた。席を立ち五歩前に進んで振り向いた。羽織ったコートと前髪がふわりと翻り、その時には千景は見知らぬ千景になっていた。 疾風ははっとして、彼女を見る。翠碧の瞳に淡い光が灯っていた。 「でも……それでも戦うというのなら、私がお相手しますから」 それは明らかに宣戦布告だった。大人達がもてはやすと同時に恐れた力を行使するという宣言だった。 疾風は鼻を鳴らして見せた。 「ふん。貴様の浅知恵ごと切り裂いてやるさ」 「……威勢の良いことだ」 一瞬後、千景は疾風の知る千景に戻っていた。 「ああそうそう、君との因縁は前世でのしがらみだと周りには説明するから、了承してくれたまえよ」 「そ、それで周りは納得するのか? まあ好きにしろ」 「ふむ。それでは帰るか。しかし今日は暑いな……」 日傘を広げる千景に、疾風は言う。 「ならばコートを脱げ」 「疾風。君は用心棒としては一流だが、探偵についての知識は幼稚園児並みと言わざるを得ないな。探偵が外でコートを脱ぐわけ無いだろう」 「知るか! しかもランクダウンしてるじゃないか!」 「気にするな。さて、今日の夕食は何にするべきか……どう思う?」 「どうって……あ、こら待て!」 とっとと歩き出す千景と、それを追いかける疾風。 昼下がりの陽光に照らされた二人の姿は、結構、仲が良さそうに見えたとか。
|