| ←前へ | 次へ→ |
ハンターシリーズ35
『ななちゃんレポート「体育大会」』
作・てぃーえむ
三町対抗体育大会。
それは文字通り、三つの町が沽券をかけて争う戦の場である。
会場は、五万もの観客を収容できるビックなドームだ。
グラウンドでは選手達が全力でぶつかり合い、観客席では、応援団が声を張り上げていた。
 そんな熱いドームのVIP席に、一つの人影があった。
そんな熱いドームのVIP席に、一つの人影があった。
年の頃なら二十歳過ぎ。鋭い顔立ちで、かなりのハンサム。しかし、瞳のない銀色の右目が違和感を発していた。
七瀬銀河。秘密組織『ハンター』のエージェントであり、普段は七号と呼ばれている。
ちなみに彼は今、仕事の最中という訳ではない。単に、体育大会に出場している同僚の写真を撮るために、最も見晴らしが良いVIP席にやって来ただけだ。
 そのVIP席には、彼以外は誰もいない。そもそも立ち入りは禁止され、扉には鍵がかかっているはずだったが、優秀なエージェントである彼にとっては障害になり得ない。
そのVIP席には、彼以外は誰もいない。そもそも立ち入りは禁止され、扉には鍵がかかっているはずだったが、優秀なエージェントである彼にとっては障害になり得ない。
彼は、望遠レンズを同僚に向けてシャッターを切りまくった。
 途中、見知らぬ可愛い女の子や、組織のアイドルであるいちごを撮っているのは、当然である。もちろんこれは後で売りさばくのだ。間違っても写真を懐に入れたりはしない。万が一、妻にばれたら、殺られるからだ。
途中、見知らぬ可愛い女の子や、組織のアイドルであるいちごを撮っているのは、当然である。もちろんこれは後で売りさばくのだ。間違っても写真を懐に入れたりはしない。万が一、妻にばれたら、殺られるからだ。
 と、彼は気配を感じた。誰かが近付いてくる。この部屋に入るつもりらしい。
と、彼は気配を感じた。誰かが近付いてくる。この部屋に入るつもりらしい。
彼はとっさに身を隠した。
 数秒後、かかっていた鍵があっけなく外され、誰かが入室してきた。
数秒後、かかっていた鍵があっけなく外され、誰かが入室してきた。
七瀬は銀の瞳が持つ力で、侵入者を視た。
 「!?」
「!?」
彼は驚いた。侵入者は知った人間だった。
浅葱千景。組織のボスがどこからか連れてきた探偵少女で、今は『ハンター本部』に居候している。お嬢様みたいな容姿に違わずおっとりとしている彼女だが、銃を持つと性格が変わる。いや、豹変する。しかも普段から銃を携帯しているので、お嬢様バージョンの彼女に会うことは滅多に無い。今回はコートを着ておらず(つまり銃を携帯しておらず)、代わりにやけにごつい双眼鏡を肩に提げている。
彼女は、向こうからは決して見える筈の無いこちらに、まっすぐ目を向けた。
「ごきげんよう。そんなところで何してるんです、ななちゃん」
気配を断っているはずなのに、バレバレだ。
彼女の能力、『感知』である。なぜ探偵にそんな能力が備わっているのかは分からない。
七瀬は苦笑しながら姿を現した。
「あー、その。ななちゃんはやめてくれないかな」
「でも、そう呼ぶように言われていますし」
「・・・ボスだな」
「はい」
千景はにっこりと微笑んだ後、七瀬の顔を見て小首をかしげた。
七瀬はすぐ、理由に思い至った。
目だ。普段はコンタクトレンズで隠している右目を視たのだ。
失態だ。
「これはその・・・」
「ああ、なるほど」
何かいい訳じみたことを言おうとしたが、それは千景の言葉で遮られた。
「水晶眼ですね」
「は?」
七瀬は、何を言われたのか分からなかった。しかし、千景は言葉を続ける。
「やっぱりあれですか。その中にはウルトプライドが入ってるんですか?」
「いや、そんなのは」
「じゃあ、イシュカルリシア?」
「・・・・・・。よく分からないけど、これは、違うよ」
首を振って否定する。
「これは、なんていうのかな。見えないはずのモノが見える、目なんだ」
「千里眼の類ですか」
「そうだね。でも・・・あまり驚かないんだね」
「そこまで驚くことですか?」
 千景は、また小首をかしげてみせた。
千景は、また小首をかしげてみせた。
「魔眼の類って、特殊能力の類でもポピュラーな方でしょう。私だって、そういった目を持ってますし」
「そ、そうなの?」
あっさりと言われて、七瀬は気が抜けた。もっと怖がられると思っていた・・・・・・。
「はい。あ、やっぱりここはいいですね。思った通り全部見渡せます」
七瀬の心中などお構いなしに、千景は窓までやって来ると、双眼鏡を構えた。
「・・・・・・そうだね」
怖がられることを恐れていた自分が馬鹿みたいだ。
七瀬は肩をすくめると、カメラを構えなおした。
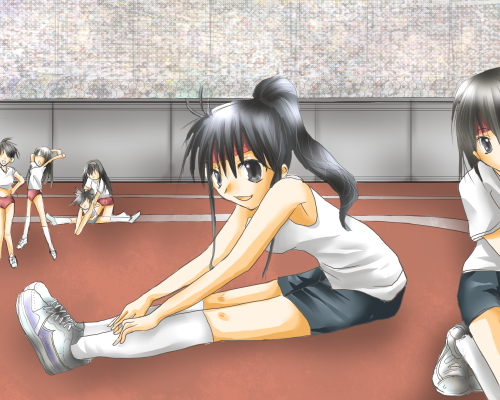 さて、グラウンドの片隅にて。
さて、グラウンドの片隅にて。
見た目十七、八の美少女が柔軟体操を行っていた。
長くつややかな髪をポニーテールに束ね、細身の肢体をスパッツとランニングシャツで包み込み、これが実に似合っている。
半田いちご。秘密組織『ハンター』のエージェントでありアイドルでもある。
他のエージェント同様、この体育大会に出場しているのだ。
 「ううぅ」
「ううぅ」
いちごのそばには、美少女、いや美幼女が、恥ずかしげにたたずんでいる。
なぜか黒いうさ耳とうさしっぽを付けていて、服装はブルマと体操着だった。ちなみにブルマの色は赤だ。
半田りく。どう見ても小学生だが組織のエージェントだ。
「おいおい。今からそんなんじゃあ、話にならないぞ」
「だって! これ恥ずかしすぎるぞ!」
「そりゃ、気持ちは分かるがな。嫌なら、断れば良かったじゃないか」
「きっぱり断った! だけどな、安土の奴がブルマを無理矢理・・・・・・」
「じゃあ、がまんしろ」
先ほどから外見にはそぐわない、荒々しい言葉使いが続いているがさもありなん、二人は元・中年男性だ。
「くううう」
りくは、顔を赤らめたままうめいた。
「ふふ。りく先輩。いい表情です」
「確かにそうですね」
七瀬のつぶやきに、千景は肯定した。
「ところでその双眼鏡。ただの双眼鏡じゃないみたいだけど」
「とっても高機能なデジカメ付きです。ちなみに倍率は十から百までです」
「ははあ。それで、どうするのかな? やっぱり売りさばくとか」
「いえ、情報収集です」
断言したが、あまり信憑性がなかった。
「あら?」
 突然、千景は声を漏らした。
突然、千景は声を漏らした。
「そんな!?」
あから様に動揺しながら、一点を見つめている。
「どうした・・・・・・。ん? あれは!!」
七瀬も、千景が見つめている人物を見つけて声を上げる。
「真城華代!?」
 「どうしたの、りくちゃん?」
「どうしたの、りくちゃん?」
いきなり声をかけられて、りくは振り返った。
「か、華代ちゃん!」
りくは驚愕した。いちごも固まった。
歩く自然災害である彼女がなぜここに?
いや、彼女に理屈を求めてはいけない。理不尽の代名詞、それが華代だ。
「なんか、ブルマが恥ずかしいって・・・・・・」
「いやいやいや、何でもないんだ」
「そう。今のところ華代ちゃんに頼るほどの事は無いんだ」
いちごとりくは慌てて手を振って、そう言った。
華代は当然、話を聞かなかった。
「またまたあ。遠慮しなくてもいいよ。りくちゃんは恥ずかしがり屋だね。でも大丈夫、あたしに任せて! あ、これ名刺ね」
「やめれええええ!」
さりげなく名刺を手渡されてしまったいちごとりくは、もう、叫ぶことしかできなかった。
 「やばい!」
「やばい!」
七瀬は叫ぶと、きびすを返した。
隣の千景も同じくだ。
二人は並んで部屋を飛び出ると、全力疾走した。
押し寄せる力を背に感じながら、非常ドアを開き、外に出る。
「た、助かった、か?」
いきも切れ切れに七瀬はつぶやいた。
「・・・ふう。大丈夫なようです」
座り込んだ千景がそう答えた。
「それはよかった・・・・・・。って、あれ、君、華代ちゃんの事知ってたの?」
七瀬はふと、千景の態度に疑問を感じた。真城華代の情報は極秘扱いされていて、組織内でも一握りの人間しか知らないはずだが。
 「知ってますよ。だから私は居候してるんです。それより、中、覗いてみませんか?」
「知ってますよ。だから私は居候してるんです。それより、中、覗いてみませんか?」
「あ、うん」
先行する千景を追い、ドームへ戻る。
で、そこで見た物は。
無数のブルマ少女だった。
しかも集団ヒステリーを起こしているらしい。なんだか、物凄いとしか言いようがない光景だった。
「・・・・・・。ここ、何人ぐらい入ってたっけ?」
「大体、五万人ですね」
ハンターが遭遇した『華代被害』の中では、間違いなくトップの被害者数である。
「これを戻すのか・・・・・・」
姿を変えられた人たちを元に戻す。それは七瀬達エージェントの仕事の一つである。
しかしエージェントの数は少なく、今回の被害者はあまりにも多い。
「一人当たり何千人だ・・・・・・?」
七瀬はため息をついて、応援を呼ぶために携帯電話を取り出した。
「あー・・・。うー」
ブルマ姿になったいちごは、訳の分からないうめきを漏らした。
 体をほぐしていた選手の皆様も、観客席にいた人たちも、審判も、もれなくブルマ少女だ。
体をほぐしていた選手の皆様も、観客席にいた人たちも、審判も、もれなくブルマ少女だ。
「これなら恥ずかしくないでしょ」
「・・・・・・。そうだね」
「喜んでもらってうれしいよ! それじゃあ、あたし、仕事があるからもう行くね!」
「うん。ばいばい」
りくは機械的に手を振り、華代は満面の笑みを浮かべて虚空に消えた。
「えー・・・、その。華代ちゃん・・・・・・話はちゃんと聞こうね・・・・・・」
そんないちごのつぶやきは、恐慌をきたしているブルマ少女達の叫びにかき消されてしまった。
かくして、三町対抗体育大会は狂乱の内に幕を閉じた。
組織は総力をあげて四万六千三十二人を元に戻し、残り四千三十一人の戸籍を改ざんした。
すべてが終わった後、組織は一時的に活動停止状態に陥った。エージェントのほとんどが過労で倒れたためである。
「ふう。全く大変だったよ。それにしても静かだね」
がらんとした食堂で、七瀬は向かいに座っている千景に肩をすくめて見せた。
テーブルには体育大会で撮った写真がずらりと並んでいた。半分は七瀬が、もう半分は千景が撮ったモノである。
 七瀬は内心でほくそ笑んだ。思いがけないトラブルがあったおかげで、なかなか面白い写真がそろっている。これなら高値で売れるだろう。妻へのプレゼントも良い物が買えるだろう。ついでに組織は休みも同然だから、安心して妻の待つ家へ戻れる。
七瀬は内心でほくそ笑んだ。思いがけないトラブルがあったおかげで、なかなか面白い写真がそろっている。これなら高値で売れるだろう。妻へのプレゼントも良い物が買えるだろう。ついでに組織は休みも同然だから、安心して妻の待つ家へ戻れる。
「まあ、みんな倒れてますから。おじ様なんて胃潰瘍で入院してますし。あ、ななちゃんもあわ雪たべます?」
千景は小皿に乗っかった、豆腐みたいに真っ白な和菓子を切り分けて、口に放り込んだ。
「いや、遠慮しとく・・・・・・てか、僕は七号です」
「相変わらず、無糖派ですね・・・・・・こんなにおいしいのに」
千景はそう言いながらも、幸せそうに頬を緩ませてお茶をすすった。ここまでやられると、本当においしいのではないかと思えてくる。
いやいや、今はそんなことはどうでもいい。
「それじゃあ、トレードといこうか」
七瀬は笑みを浮かべると、交渉を開始した。
| ←前へ | 作品リストへ戻る | 次へ→ |